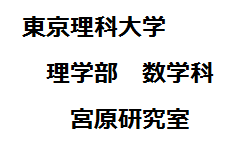管見「イングランド王国」(平成20年浩洋会例会講演)
昨年の浩洋会例会における講演「歴史の“バトンタッチ”」において、筆者はイギリス王朝の系譜について簡単に述べた。そこで、今回は、その続編のような意味で、イギリス王国の歴史についてもう少し詳しい考察を試みることにした。その中心的なテーマは、そもそもイギリス人とは人種的に言っていかなる民族なのか、一体彼らはどこから来てどのような歴史を辿ったのか、ということである。これは、簡単には答えられない、非常に難しい問題であるが、大変に面白い問題でもある。これについて、浅学の筆者は、多くの誤解と独断を持っているであろうと思われ、未熟な管見と言われてもしかたがないのであるが、あえて拙論を述べることにした。この小文において、イギリス王国の全歴史を紹介することはもちろん不可能であるし、もともと、そのような意図は持っていなかった。本稿は、筆者が、上記のテーマにおいて、同王国にとって最も核心的だと思うところを書いたものである。
1. ブリトン人とアングロ・サクソン人
現在のグレート・ブリテン島には、新石器時代より、ヨーロッパ大陸から渡って来たケルト人が住みついていた。ローマ人はこの島をブリタニアと呼び、主にその南部に住む人々をブリトン人と呼んだ。北部には、ケルト系のピクト人やアイルランドからやって来たスコット人が住んでいた。紀元1世紀の中頃には、ブリトン人たちはいくつかの部族ごとにそれぞれ小さな王国を作り、それらがブリテン島南部に割拠していた。紀元43年、ローマ皇帝クラウディウスは、ブリタニアの豊富な鉱物資源や農産物を目当てに、ブリタニア征服を成功させ、それ以後ブリタニアはローマ帝国の属州となったのである。130年頃には、皇帝ハドリアヌスによって、北方のピクト人やスコット人の攻撃を防ぐために、ブリテン島を東西に走る長大な「ハドリアヌスの壁」が建設された。しかし、結局、ローマのブリタニア支配は4世紀末で終る。帝国の勢力衰退に伴い、大陸では、4世紀末には北方のゲルマン諸族が、大挙してライン河やドナウ河を渡り、続々と帝国所領に侵入を始めた。いわゆる「ゲルマン民族の大移動」である。ブリタニアに駐屯していたローマ軍は、蛮族の侵略防衛のために、大陸に送られることになり、407年頃にはブリタニアを完全に撤退してしまった。この頃、ブリタニアにおいても北ゲルマンの地から海を越えてやって来るアングロ・サクソン人(これもゲルマン人であって、アングル族とサクソン族の混成集団である)の襲撃が次第に激しくなってきていたが、ローマに見放されたブリトン人は自力で防衛しなければならなかった。しかし、彼らの武力では抵抗し難く、幾多の激しい戦いの末、ブリトン人の大半は西方のウェールズやアイルランドに移動せざるを得ず、また、彼らの一部分は、さらにブリテン島西南部のコーンウォール半島から海を渡って、現在のフランスのブルターニュ地方へと逃れたのである。ブリタニアに残ったブリトン人はアングロ・サクソン人の中に吸収され、両者の同化、融合が進んだ。ブリトン人を西方へ追いやったアングロ・サクソン人たちは、ブリタニアにおいて、部族ごとに分かれて七つの王国(ケント、サセックス、ウェセックス、エセックス、イーストアングリア、ノーサンブリア、マーシア)を創った。それは5世紀末頃のことであるが、それ以後この分立状態が続くおよそ3世紀半ほどの期間を「イングランドの七王国時代」という。そして遂に、829年にウェセックス王エグバートが七王国を統一し、アングロ・サクソン王国を建国した。ここから統一イングランドの歴史が始まるのである。
2. ヴァイキングの侵略
しかしながら、この統一が成された頃から長期にわたり、イングランドは極めて過酷な仕打ちに翻弄される運命にあったのである。それは北方の蛮族ヴァイキングの来襲であった。ヴァイキングと言うのは、スカンディナヴィア半島あるいはユトランド半島に住んでいたゲルマン人を漠然と指す名称であって、ノルマン人とも言い、その起源においてはアングロ・サクソン族と同根の人種である。793年、リンディスファーン島(イングランド北東岸沖の小島)の修道院が、突如として、船団を組んでやって来たノールウェー人の集団に襲撃された。彼らは、ノールウェー南部に複雑に入り組んでいるフィヨルドの一つに、根城を持つ部族の一味であったらしい。翌年もまたその翌年も、イングランド東岸の修道院や教会が次々にヴァイキングの攻撃を受け、宝物は略奪され、修道士や住民は虐殺された。さらに、少し遅れて、今度はユトランド半島に住むデーン人(デンマーク人)の海賊たちが襲来した。やがてヴァイキング同士の抗争が始まり、時を経て、主として、ノールウェー人のヴァイキングはアイルランドを、デーン人のヴァイキングはイングランドを襲撃するようになった。そして、絶えず押しかけて来た彼らは、それぞれアイルランドおよびイングランドの地に定住し始め、そこを基地として略奪の行動範囲をさらに拡大していったのである。ちなみに、アイルランドの首都ダブリンやイングランドの古都ヨークは、それぞれノールウェー人とデーン人が占領し、彼らがその後発展させた町である。さらに、デーン人は、イングランドにおいて広大な土地を奪い取り、自らの領土となした(これをデーン・ローという)。そして、遂には、一時的ではあったにせよ、アングロ・サクソン王国はデーン王朝に乗っ取られるという由々しい事態が生じたのである(1016~1035)。ノールウェー人とデーン人のヴァイキングの活動はまことに凄まじく、イングランドやアイルランドだけでなく、彼らは、西ヨーロッパの要所々々に砦を建設しそれらを拠点として、ドイツ、フランスは言うに及ばず、遠くはスペイン、イタリア、北アフリカにまで攻撃の手を広げ、強奪、虐殺をほしいままにした。豊かな商業都市であった北海沿岸のドレスタッドやカントヴィックのように、彼らの再三の襲撃を受け、消滅してしまった町も少なくなかった。実に驚くべきことに、リンディスファーン島の攻撃以来、このような惨事が約200年もの長い間絶えることなく繰り返されたという。
残虐なヴァイキングであったが、他面、彼らは、高い文化水準を持った民族であった。詩歌や散文などの文芸、木彫や貴金属細工などの美術、毛織技術、鍛冶技術などに優れていたが、特筆すべきは、造船技術と航海術である。オスロ近郊のヴァイキング船博物館には、19世紀末から20世紀初頭にかけて発掘され復元された、3隻の見事な造りのヴァイキング船が展示されている。それらは、オスロ近辺の墳墓より掘り出されたもので、身分の高い人たちの棺として使用されていたのである。歴史家の推定によると、それらは、ちょうどヴァイキングが略奪行為を開始した800年頃から850年頃にかけて造られたものであった。また、磁石や羅針盤のない時代に彼らが考案した、分度器など方向や緯度を計測するための木製の簡単な測定機器も発見されている。それらを駆使して彼らは、ヨーロッパの町々を目指し、襲撃、略奪、あるいは土地の強奪(移民)を行った。さらに彼らは、それだけではなく、西方の海に乗り出し、新地開拓事業を始めたのである。820年頃にはアイスランドを発見、植民を行った。彼らはさらに西進し、980年頃にグリーンランドを発見、この酷寒の地においても植民が行われた。けれども、その移民の子孫は、故国に見捨てられ、いつしか死に絶えてしまった。今日、彼らの住居や教会の遺構が発掘されている。そしてまた、今に残るアイスランド人の散文物語「サガ」は、彼らのある者が大西洋を横断し、現在の北アメリカのニューファウンドランドと思われる地に到達したことを伝えている。そればかりでなく、長い時間をかけて集められた数々の証拠がそれが真実であることを示しているのである。それは、西暦1000年頃のことであり、コロンブスらによる新大陸発見よりもおよそ500年も前のことであった。こうしてみると、ヴァイキングの凄まじいばかりのエネルギー溢れる行動を、単なる襲撃、略奪という海賊行為と見なすよりも、むしろ、かつてゲルマン諸族が行ったような民族移動という概念において捉える方が妥当であろう。ヴァイキングの活動は、言ってみれば、第二次のゲルマン民族の移動であったのである。
3. ノルマンディー公のイングランド征服
フランス王国においても被害は甚大で、885年にはセーヌ川を遡って来たヴァイキングの大軍によって首都パリが攻囲されるという重大な事件が起こった。時のパリ伯ウード・カペーの必死の防戦の甲斐あって、パリは辛うじて陥落の憂き目を見ずにすんだ。ヴァイキングの度重なる執拗な攻撃に手を焼いたフランス王シャルル3世(単純王)は、911年、当時セーヌ川の下流地域に、先住民を追い出し住みついていたヴァイキングの首領ロロに、正式にその地方全体を封土として与え、その代わりにノルマンディーの沿岸防備の任務を負わせることとした。これが、以後その地に多くのノルマン人が定着したノルマンディー公国の誕生であった。言うまでもなく、ノルマンディーとは、ノルマン人にちなんだ地名である。初代のノルマンディー公となったロロがノールウェー人であったかデーン人であったかについては明確ではないが、彼の軍隊はその大部分がデーン人であったということである。ロロは、フランス国王の封臣として王に助力することにより、領地を現在のノルマンディー地方の大部分にまで拡大し、次第にその勢力を強化していった。それ以後この地方には北方のノールウェー人やデーン人が続々と移住して来たが、この地の民衆のキリスト教化、フランス化が急速に進んでいった。すなわち、異教徒であったノルマン人たちは速やかにキリスト教に入信し、母語を捨ててフランス語を用いるようになったのである。
ロロから数えて六代目のノルマンディー公ウィリアムの時代(11世紀中期)には、既にノルマンディー公国はフランス国内でも有数の富裕な強国に成長していた。ウィリアムは、英仏海峡を隔てた、まさに一衣帯水の地イングランドを獲得すべく、秘かにその機会を窺っていた。そのいきさつは次のようなものであった。当時のアングロ・サクソン王エドワード(懺悔王)(在位1042~1066 )の母は、ノルマンディー家の出身であって、ウィリアム公の大叔母に当たり、エドワードとウィリアムは旧知の仲であった。エドワードには子がなく、彼は自分の死後には王位をウィリアムに譲るという約束をしたのである。それは、かつてエドワードが、母の故郷であるノルマンディーに亡命していた時に、ウィリアムより受けた恩義に報いるためであった。ところが、エドワードの死後すぐに、彼の直臣の子で王族の血縁者ではないハロルドなる者が、エドワード王の遺言であると称して王位についてしまった。そこで、ウィリアムは、エドワードとの先の約束を楯に取り、イングランド王の後継者は自分であるとのローマ教皇の認可をも抜け目なく取りつけて、イングランド進攻を正当化し実行に移したのである。1066年、彼は、800隻の船団を率いて英仏海峡を渡り、有名なヘイスティングズの戦いにおいてハロルドを打ち破って、イングランド征服を成し遂げた。彼は征服王ウィリアム1世(在位1066~1087)として、イングランドにおけるノルマン王朝の祖となった。この出来事はイングランド史の一大転換点であった。何しろ、それは、フランスのノルマンディーの地から海を渡って攻めて来た騎士たちによるイングランド征服であったのだから。イングランドを統治するに当たって、ウィリアム1世は、アングロ・サクソン人の人口の10%にも満たない支配者ノルマン人の立場を守るために、ノルマン人に有利な法令を制定し施行した。そして、旧来のアングロ・サクソン貴族は少数の例外を除いて追放され、短期間に、王国全土における大規模かつ徹底的な征服活動が行われた。こうして、上位聖職者も含めた支配者層が、完全にノルマン人によりとって代わられたのである。望みどおり、ウィリアムはイングランド王となったが、彼はまだ依然としてノルマンディー公でもあった。すなわち、彼はイングランド王であると同時に、フランスに領地を持ち、フランス王の臣下でもある、という前例のない事態が生じたのである。彼の後継者たちの時代にあっても、このような異例の状態が長く続き、将来のイングランド、フランス両国にとって恐るべき禍根を残した。
ここまで述べてきたことから容易に理解されるように、イングランド人は、ヴァイキングの血を濃厚に引き、ある意味でその正統な子孫であると言ってもよい民族である。イングランド王国は、この後1000年に近い歳月の間、ヴァイキングの末裔に相応しく、まさに波瀾万丈の動乱の歴史を辿り、今日に至っているが、その王朝は、血筋が絶えることなく、イギリスの現女王エリザベス2世(在位1952~)に至るまで連綿として続いている。
4. 英語の変遷
アングロ・サクソン王国がデーン人の攻撃に痛めつけられていた9世紀末頃、一人の優れた王が現れた。それは、統一者エグバート王の孫に当たるアルフレッド大王(在位871~899)であった。彼は、イングランドに定住しているデーン人の度重なる攻撃によく耐え、883年頃にはロンドンを奪回し、886年頃に休戦協定を結んだ。アルフレッド王の時代は、デーン人の来襲に備えて国を上げての防衛体制が整えられ、また、組織的な政治機構が作られるとともに、国家意識が高まっていった時代であった。それは、アルフレッド王の法典編纂やアングロ・サクソン文芸の奨励に、窺い知ることができる。彼は、古い法典や諸地域の法典を集大成し、それを王国全土に適用されるべきものとした。また、文武両道に秀でていたアルフレッド王は、衰退していたキリスト教文化の伝統を回復するために、学者や聖職者の助けを借りて、ラテン語の蔵書を英語(アングロ・サクソン人が用いていた古代英語)に翻訳する仕事に自ら取り組んだ。この国では、同時代の大陸の諸王国が、母語を捨ててラテン語を国家の言語として採用していたようなことは行われず、ラテン語による学者的文芸と並んで英語による民衆的文芸が発達した。また、法典編纂においても、ラテン語ではなく英語が使用されたのである。ゲルマン民族の侵入後に建国された諸王国の中で、アングロ・サクソン王国はローマ化されなかった唯一の国であった。
さて、現代英語は、この古代英語が他の言語に影響され、幾多の変遷を経た果てに、ようやくにして辿り着いた言語なのである。もともと、アングロ・サクソン人は征服したブリトン人の言葉の影響を受けたことはほとんどなかった。9~10世紀には多数のデーン人がイングランドに侵入し定住したが、アルフレッド王は戦いに勝ってもデーン人を駆逐しなかったので、彼らはアングロ・サクソン人と共に暮らし、その中に溶け込んでいった。そして、両者の共存の結果、デーン人が話していた北欧語(英語と同系のゲルマン語)は英語に多大の変化をもたらした。文法の異なる二つの言語が同時に用いられた時に、必然的に、意味を正確に伝えることが優先されたために、例えば形容詞や動詞の語尾変化が見られなくなるなど、文法の形式が軽視され次第に単純化していったのである。さらに時代は下って、ウィリアム王の征服以来、イングランドにはおびただしい数のノルマン人が流入してきたが、当然、宮廷や貴族社会において用いられた言葉はフランス語であった。そればかりでなく、13世紀までは、フランス語がイングランドにおける公用語として定められ、使用され続けたのである。従って、アングロ・サクソン人が上流階級にのし上がるためには、フランス語を必死に学ばなければならなかった。また一方では、文学の分野においてフランス語の単語や表現が豊富に取り入れられ、その多くが次第に一般民衆の日常語の中にも浸透していった。このように、フランス語の英語に対する全般的な影響は、かつての北欧語のそれに劣らず極めて大きく、フランス語の単語は英語の語彙の約50%を占めるまでになったのである。そしてまた、この場合にも、名詞の性の消滅や仮定法の消滅など、文法の単純化が大いに進んだ。こうして、英語は、9世紀以来、複数の異民族がイングランドに押し寄せて来て、長期にわたり激しく揉まれ続けたあげく、アルフレッド王時代の古代英語とは似ても似つかぬ言語に変容してしまった。それがさらに変移を遂げて、今日の英語ができ上がったのである。現代英語が、他のゲルマン系諸国の言語と比較するとき、似たところはあるけれども、かなり趣を異にする特殊な言語であるのは、このような事情によるのである。
5. ハノーヴァー王朝
アングロ・サクソン王朝を倒し、イングランドを支配したノルマン王朝は、ウィリアム征服王より三代目にして、男子の後継者を失う羽目となり、やむなく、フランスのアンジュー家へ嫁いでいた王女マティルダの息子をイングランド王ヘンリー2世(在位110~1035)として迎えることになった。これより後にも、イングランド王家においては、他家から血縁にある者を王として迎え入れるという事態が三度生じている。イングランドの貴族チューダー家から王に成り上がったヘンリー7世(在位1485~1509)、スコットランド王家から迎えられたジェームズ1世 (在位1603~1625、この王はスコットランド王をも兼ねた)、ドイツのハノーヴァー家から招かれたジョージ1世(在位1714~1727)が、その三人の王たちである。上記のジェームズ1世以来、アン女王(在位1702~1714)の時代に至るまで、イングランドとスコットランドは互いに独立国でありながら同一の君主を戴く、という異例の状況が続いたが、遂に1707年、両王国は正式に合同し、グレート・ブリテンと称することになった。
ところが、女王アンは次々と子を失って世子がいなくなり、その死後、幾人かの候補の中から後継者に選ばれたのは、イングランド王家の血筋を引きドイツのハノーヴァー選帝侯家に嫁いだゾフィーの息子ゲオルク(前記のジョージ1世)であった。当時、ハノーヴァー家には、かの万能の大学者ゴットフリート・ヴィルヘルム・ライプニッツ(1646~1716)が、図書館長として召し抱えられており、ハノーヴァー家の出自であるヴェルフェン家の歴史編纂の仕事を命じられていた。ヴェルフェン家と言えば、過去1200年にもわたる伝統を持ち、ドイツにおける由緒ある最古の貴族家門の一つであり、他のいかなるヨーロッパの貴族家系もこれを凌駕するものはないのである。同家は皇帝を一人しか生み出さなかったが、皇帝の座をめぐる争いに端を発したホーエンシュタウフェン家との長年にわたる宿命的な確執は歴史上有名な事実であり、両家の間のこの紛争は、後に全ヨーロッパを巻き込んだ皇帝派と教皇派の間の闘争にまで進展した。さて、ライプニッツは、君命を果たすべく、多方面にわたるヴェルフェン家の膨大な史料を精力的に収集したが、同家の史書執筆は、彼の哲学研究が優先されたために進捗せず、彼の生前には完成に至らなかった。そのせいでもあるまいが、気の毒なことに、彼は当主ゲオルクに疎まれていた。他方、ゲオルクの母ゾフィーは、彼に厚い信頼を寄せ、彼を政治顧問として遇し、種々の進言を受け入れていたのであったが。ゲオルクに嫌われていたライプニッツは、ゲオルクがイギリス王ジョージ1世としてロンドンへ赴く際には、随行員の中に加えて貰えず、ドイツに残った。もし、このとき彼が王と一緒にロンドンへ行っていたならば、彼はニュートンに会って会話を交わしたかも知れないし、そうしたならば、微分積分学の創案をめぐり、対立した彼らの学派間の争いのわだかまりも、ひょっとすると溶けたかも知れない。あるいは、もし彼がイギリス王の重用する学者であったとするならば、彼は、イギリスの学界においても重きをなす存在となっていたであろうし、晩年を安らかに過ごすこともできたであろう。しかし、ライプニッツの保護者であったゾフィーの死後には、彼の支援者はいなくなり、その価値ある研究の大部分は発表の機会もなく、あれほどの大学者が不遇のうちに死んだという。
ジョージ1世よりヴィクトリア女王(在位1837~1901)までのイギリス王朝は、ジョージ1世の出身家名をとってハノーヴァー王朝と呼ばれている。現女王エリザベス2世はヴィクトリア女王の玄孫(曾孫の子)である。この王朝には不肖の王も多く現れたが、ヴィクトリア女王の治世において、イギリスは未曾有の繁栄の時代を迎えた。この時代に同国は、世界で最初に産業革命を成し遂げ、綿工業の発展に続いて、鉄と石炭を利用した種々の重工業を発達させ、世界一の海運国として自由貿易のネットワークを確立した結果、長らく世界経済に君臨した。同国は、南北アメリカ、アフリカ、オーストラリア、ニュージーランド、中東、アジアなどにおける広大な諸地域を植民地として獲得し、「日の沈まぬ大英帝国」と称賛された。しかし、同国は、第二次世界大戦終了後は、国力衰退を来たして、次々に植民地を手離す羽目となり、さらに無謀な政策と惨めな失敗によって権威をすっかり失い、かつての栄光の大英帝国は終焉を迎えた。
第4節英語の変遷に関する注釈
1. 西暦1000年頃の英語
次のものは、ある修道士によって、1000年頃に書かれた古代英語の説教文の一節である。現代英語とはほとんど関係のない言語に見える。これはノルマン人の征服以前の英語である。
Tha the ne gelyfath thurh agene cyre hi scoriath, na thurh gewyrd; for-than-the gewyrd nis nan thing buton leaswena: ne nan thing sothlice be gewyrde ne gewyrth, ac ealle thing thurh Godes dom beoth geendebyrde, se the cwaeth thurh his witegan, ‘Ic af andige manna heortan , and heora lendena, and aelcum sylle aefter his faerelde, and aefter his agenre afundennysse’.
2. 14世紀の英語
アルフレッド大王の孫に当たるエセルスタン王(在位925~939)も、学問を積極的に奨励した王であった。この王の時代に、ユークリッドの幾何学がイングランドに紹介された。その事実を、14世紀のある詩人が次のような詩に書いている。この詩が書かれた時代はノルマン人の征服以後約200年を経ており、英語は、フランス語の影響を受け、現代英語にかなり近いものに変化していることが見てとれる。明らかに、y = i である。
Thys grete clerkys name wes clept Euclyde,
Hys name hyt spradde ful wondur wyde.
The clerk Euclyde on thys wyse hyt fonde,
Thys crafte of gemetry yn Egypte londe;
Yn Egypte he tawzhte hyt ful wyde,
Yn dyvers londe on every syde …..
Thys craft com ynto Englond as y zow say
Yn tyme of good kynge Adelstonus day.
3. チョーサーの英語
次の英文は、近代英語の基礎をなしたと言われているG.チョーサー(c.1340~1400)の有名な「カンタベリー物語」のプロローグの一節であるが、これは、注2のものよりも新しく、より現代英語に近い。
And Frensh she spak ful faire and fetisly,
After the scole of Stratford atte Bowe,
For Frensh of Paris was to hir unknowe.
(平成20年11月記す)