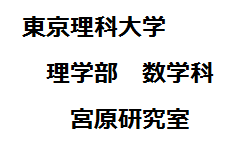王の離婚 (平成26年浩洋会例会講演)
近世以前のヨーロッパにおいては、カトリック教会の支配力が極めて強く、人々の日常生活全般に大きな影響を及ぼしていた。例えば、夫婦が離婚したいと望んでも、教会の許可を得なければ不可能であった。特に王侯貴族が正式に離婚を実現したいと思えば、ローマ教皇の認可を得る必要があり、そのために彼らは大変な労力を費やさなければならなかった。彼らが、苦労しながらも何とか上手に立ち回り、離婚を勝ち取ったという事例は非常に少ないと思われるが、ここではそのような三つの例を挙げてみたい。
1 フランス王ルイ12世(在位1498~1515、享年52)
先王シャルル8世は、ナポリ王国の相続権は自身にありとの名分のもとに、同王国制覇を目指し1494年、9万の大軍を率いて威風堂々と遠征を敢行した。しかし、それに反発した諸国の反フランス同盟が結成されたことを知り、周章狼狽してナポリからフランスへ逃げ帰った。彼は失意のうちに1498年死去した。彼には男子がいなかったので、次の王にはヴァロワ朝傍系のルイ(12世)が即位した。ところで、ルイの妻ジャンヌは、シャルル8世の姉であり、身体障害者(せむし)であった。シャルル8世の亡父ルイ11世は、暴君と呼ばれた専制君主で、悪辣な政略をほしいままにしていた王であったが、娘ジャンヌと当時はオルレアン公であったルイ(12世)とを、有無を言わせず強制的に結婚させていたのであった。
一方、シャルル8世の妻アンヌは、フランス王妃であると同時に、ブルターニュ公国の領主をも兼ねていた。そこで、ルイ12世は、ブルターニュ領有を目論み、正妻ジャンヌを離婚して、未亡人となったアンヌと結婚しようと企んだ。ジャンヌとの離婚にはローマ教皇の許可が絶対に必要であった。当時の教皇は、ボルジア家出身の悪名高いアレクサンデル6世である。ルイはアレクサンデルに接近し、離婚の承認を求めた。アレクサンデルは、その見返りに、長男チェーザレに領地と爵位を与えることなど種々の虫のよい要求を突きつけたが、ルイはこれを承諾し、両者の間に協約が成立した。かくして、ルイ12世は、始めの目論見通り、王妃ジャンヌと正式に離婚し、ブルターニュ公国の領主アンヌと再婚することができたのである。
ルイとアンヌの間にはクロードとルネという二人の娘が生まれたが、男子を授からないまま、王妃アンヌは病死してしまった。どうしても世継ぎの欲しいルイは、第3節に登場するイングランド国王ヘンリー8世の妹メアリー王女を3人目の妻として迎えた。このとき、ルイは既に52歳となっていたが、花嫁は芳紀まさに16歳、しかも絶世の美女であったと伝えられている。ところが、ルイは、盛大な結婚式の後、わずか3か月にして死去したのである。当時のある伝記作者は、「王は全精力を使い果たして死んだ」と記しているという。
ちなみに、ブルターニュがフランス王国の領土となるのは、ルイの娘クロードと結婚した次期の王フランソワ1世の時代のことである。
2 フランス王アンリ4世(在位1594~1610、享年56)
フランスのヴァロワ王朝は、フィリップ6世(1328年即位)以来およそ260年間続いていたが、フランソワ1世の孫たちが次々に早世し、アンリ3世の死(1589年)をもって、その血統が絶えてしまった。そこで、次の王位継承者として、フィリップ6世の曽祖父ルイ9世の末子ルイ・ド・ブルボンの末裔であるナヴァール王アンリに白羽の矢が立った。フランス王アンリ4世の誕生である。これがブルボン王朝の始まりであって、彼の孫に当たる太陽王ルイ14世の時代には絶対王政が確立し、同王朝は栄華を極めた。アンリ4世はもともと新教徒(ユグノー教徒)であり、その首領と目されていた。当時フランスでは、カトリック教徒とユグノー教徒の間に激しい闘争が繰り広げられていた。そこで、既に1572年に、王室のユグノー教徒懐柔策として、新教徒の頭目であるアンリ4世は王妹マルグリットと政略結婚させられていたのであった。そして、その結婚の祝宴に全国から集まったユグノー教徒の貴族たちを始め、パリ在住のユグノー教徒たちを、カトリック教徒たちが大量虐殺するという酸鼻を極める大事件が起こった(聖バルテルミーの大虐殺)。アンリ4世は、両教徒の争いを終結させるため、また、王位に就くために、自らカトリックに改宗し、1594年、正式にフランス王となった。
アンリ4世の妻マルグリットは色情狂と言われるほど多数の愛人を持っていたし、一方、夫のアンリも多情な男で、女性関係が乱脈であったので、夫婦仲がうまくいくはずはなかった。マルグリットは、夫の冷たい仕打ちに我慢できず、とうとう夫の敵側の陰謀に加担したために捕えられ、オーヴェルヌ山中のユッソン城に軟禁されてしまった。こうなっては離婚しか考えられないが、ローマ教会の認可を得ることが難しく、この交渉は難航した。結局、教会は、離婚理由として、この二人は血族結婚であること、同棲生活が極めて短く王朝を継ぐべき子がいないことなどを認め、正式の離婚が成立した。その際、マルグリットには、離婚後も「王妃」の肩書を使用することとパリで生活することが認められた。その後、アンリ4世はトスカーナ大公メディチ家出身のマリーと、持参金目当ての再婚をし、後継者ルイ13世を儲けた。アンリ4世は、1598年には宗教の自由を認める「ナント勅令」を発したが、狂信的なカトリック教徒に付け狙われ、遂に暗殺された。
3 イングランド王ヘンリー8世(在位1509~1547、享年58)
ヘンリー8世は、イングランド王国チューダー王朝の祖ヘンリー7世の次男として生まれた。当時のイングランドは、二つの大国フランスとスペインに挟まれた小国に過ぎなかった。ヘンリー7世は、スペインとの同盟を求め、1501年、長男アーサーをスペイン王女キャサリンと結婚させた。ところが、その翌年、アーサーが死去したため、ヘンリーは皇太子となったが、兄嫁であったキャサリンと結婚させられることになった。このキャサリンは、有名なスペイン女王イサベルの娘であり、後に神聖ローマ帝国皇帝として実力を振るったカール5世の叔母に当たる。ヘンリー8世と妻キャサリンの間には6人の子が生まれたが、次々に死産あるいは夭死し、一人の女子(後の女王メアリー)だけが残った。ヘンリーは、キャサリンからの男子出生をあきらめ、キャサリンの侍女アン・ブーリンに関心を寄せるようになった。彼はアンとの結婚を望み、キャサリンとの離婚を画策した。
ところが、キャサリン自身は離婚を拒否し、また、彼女の甥である皇帝カール5世は、ローマ教皇に圧力をかけ、ヘンリーの離婚交渉を妨害した。そして、教皇も今を時めく皇帝と事を構えることを避け、離婚を認めようとはしなかった。いらだったヘンリーは、遂に1534年、イングランド王国とローマ教皇庁との縁を切り、「国王至上法」を発布して、ローマ・カトリック教会とは独立の「イングランド国教会」を設立した。この教会の長も国王ヘンリーが兼ねるというとてつもない大変革であった。このような極めて乱暴な荒療治によって、教皇庁と決別し自由になったヘンリーはアン・ブーリンとの正式の結婚にこぎつけたのである。この二人の間に生まれた娘が、後年イングランド王国に大繁栄をもたらすことになる女王エリザベス1世であった。
その後、ヘンリーは別の愛人を王妃に据えるために、アン・ブーリンの姦通事件をでっち上げ、彼女を処刑した。そして、何と処刑の10日後にその恋人と結婚したのである。それからも、彼は次々と妻を取り換え、最後の王妃キャサリン・パーは6人目の妻であった。ヘンリー8世は中世からルネサンス期までのヨーロッパにおける最悪の暴君である。彼は、幾人かの王妃たちに対して残酷な仕打ちをしたのみならず、政治や外交などにおいて、彼の考えに反対する者を、それが重臣であろうが聖職者であろうが、容赦なく次々に処刑した。そのような憂き目に会った家臣たちは3万人にものぼるだろうという説もある。第一の正妻であったキャサリンとの離婚とアン・ブーリンとの再婚に反対し、また、教皇庁に対するヘンリーの変革に異を唱えた有名なトマス・モア(名著「ユートピア」で知られる思想家でもある)は、反逆罪の烙印を押され処刑された家臣の一人である。頑健な肉体の持主であったヘンリーも、当時ヨーロッパで流行していた梅毒に感染してからは、とみに身体が衰弱し、58歳にして死亡した。
参考文献
1 武部好伸 「フランス・ケルト紀行~ブルターニュを歩く」 彩流社
2 佐藤賢一 「王妃の離婚」 集英社文庫
3 塩野七生 「チェーザレ・ボルジアあるいは優雅なる冷酷」 新潮文庫
4 渡辺一夫 「ルネサンス雑考(上巻)」 筑摩書房
5 渡辺一夫 「戦国明暗二人妃」 中央公論社
6 アレクサンドル・デュマ(榊原晃三訳) 「王妃マルゴ(上・下巻)」 河出文庫
7 森護 「英国王室史話(上巻)」 中公文庫
8 河北稔編 「イギリス史」 山川出版社
(平成26年11月記す)