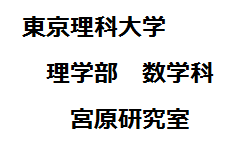古代ギリシアの詩人たち
若い頃、私はドイツ歌曲が好きで、いろいろな曲を聴いては楽しんでいたものである。当時はレコードの時代であった。1960年代、有名なバリトン歌手ディートリヒ・フィッシャー=ディースカウの最盛期の歌唱による、それまで日本人の誰もが聴いたことがないようなドイツ歌曲のレコードが次々に発売されていた。それら数多くの曲の中に、「アナクレオンの墓」という歌があった。それは、ヴォルフガング・ゲーテの短い無韻の詩に、フーゴー・ヴォルフ
が作曲したものである。その曲は、テンポがゆったりとして、音の高低や強弱を抑え、極めて静謐な趣を湛えたものであった。この詩の情景や
雰囲気を 非常に良く表現した佳曲であると思う。一方、ゲーテが、どのような状況でどのような感情を抱いてこの詩を作ったのかについては
よく分からない。
ゲーテの詩は難解なのでその真意を把握することも難しいが、とりあえず、その詩を訳してみると、大体次のような意味になるだろう。
- アナクレオンの墓
- ここは、薔薇が花咲くところ、
- 葡萄の木と月桂樹が絡まるところ、
- 雉鳩が雛を呼ぶところ、
- 蟋蟀が鳴き合うところ、
- ここは、神々が精魂を込めて美しく
- 木々を茂らせ飾り立てているのだ。
- これは、一体全体、誰の墓なのだ?
- それは、アナクレオンの安らぎの住処である。
- この幸せな詩人は、ここで、春、夏、秋を楽しんだ;
- そして冬には小高い丘が彼を確と護っている。
この曲に出会った頃には、私は「アナクレオン」という詩人が一体、どの国の、どの時代の人物であるのか全く知らなかった。その後、調べたところ、この詩人は、古代ギリシアの七大抒情詩人の一人であることが分かった。岩波文庫の、呉茂一訳「ギリシア抒情詩選」及び「ギリシア・ローマ抒情詩選 花冠」を読み、詩人の経歴のあらましや作品の一部を知った。アナクレオンは、今からおよそ2600年ほど前にイオニア地方(現在はトルコ領)に生まれ、若い頃に始まったペルシア戦争(紀元前500~479年)を避けて、トラキア地方のアブデラ(現在ギリシア北部)に移り住んだ。その後、彼は、数学者ピタゴラスの出身地として有名なサモス島の宮廷に仕えた後アテネに移住するが、この間、主に酒宴や恋愛の歌そして頌歌を詠み、自由と享楽を求める詩人として盛名を馳せた。当時としては極めて長寿の80余歳まで生き、老境を歌った詩もあるので、晩年まで詩作を続けていたらしいが、人生を大いに楽しんだ詩人であった。この大詩人は後世にも大きな影響を与え、彼の詩風を真似たアナクレオン風歌謡(アナクレオンテア)が長い間流行した。中には、彼の真作として通用したものもあったという。また、彼が葬られた塚は石を載せただけの質素なものであったというが、葡萄の木や月桂樹の美しく茂り合う墓の情景が詩に歌われるようになり、「アナクレオンの墓」は近世に至るまで好んで詩歌に詠まれる題材となった。上記のゲーテの詩も、たぶんこのような風潮に乗って作られたものであろう。
前述の訳者呉茂一(くれしげいち、1897~1977)は我が国の古代ギリシア・ラテン文学の権威として知られ、多数の著書、訳書を持つ。この大家は、明治期に有名であった精神医学者呉秀三の長男として東京に生まれ、父の希望により医科に進学するが、作家の有島武郎や歌人の斎藤茂吉との交流があり、その影響を受けて、中途で文学の道に転ずる。西洋古典の研究を始めるようになったのは、古典ギリシア詩の彼の和訳を茂吉が激賞したのがきっかけであったという。呉茂一の家系には、著名な学者が多数居並び、例えば、幕末の名だたる蘭学者箕作阮甫(みづくりげんぽ)は彼の母方の曽祖父に当る。ちなみに、阮甫は、明治期日本の数学の草分けにして文部大臣にまで任ぜられた菊池大麓(だいろく)の祖父でもあり、そして大麓の四男菊池正士は物理学者として大成し東京理科大学第3代学長を務めた。ついでながら、阮甫と、かの海舟勝麟太郎との間の面白いエピソードが伝えられている。少年時代に蘭学を志した麟太郎は阮甫宅を訪れ、玄関先にて丁重に入門を乞うた。この少年の度重なる熱心な願いに対して、阮甫は傲岸な嘲笑的態度に終始し、「江戸人は嫌いだ」、「江戸人は軽薄で蘭学などやっても長続きしないから止めておけ」などと頭ごなしに言う。この言葉にひどく傷つけられた麟太郎は、憤然と「先生にできる蘭学が江戸人にできぬという法がありましょうか」と言い返し、とっとと門外に出たという(子母澤寛「勝海舟(一)」より)。
話を元に戻すが、古代ギリシア・ラテン詩の呉茂一訳は本当に素晴らしいものである。終生たゆむことなくギリシア・ラテンの古典研究に一身を捧げたこの碩学の業績には頭が下がる。古代ギリシア語・ラテン語からの和訳に際して、原詩の持つ雰囲気をできる限り損なわぬように、語句や文字を慎重に選び、修辞に懸命の努力をされたことが、いくつかの訳詩をじっくりと読むことにより少し理解できるような気がする。まさしく彫心鏤骨の訳業だと賞賛されている。また、そればかりでなく、古代の詩人についての解説や各詩への注釈におけるご本人の文章自体が、得も言われず魅力的で、何度も読み返したくなるような名文なのである。私たちより一世代以上前の文人の文章らしく古めかしいが、独特の重厚な文体が味わい深く、また簡潔な表現ながら語彙の多彩なることにも感嘆させられるのである。
それでは、前記2冊の呉茂一訳詩集
- A「増補 ギリシア抒情詩選」(岩波文庫)、
- B「ギリシア・ローマ抒情詩選 花冠」(岩波文庫)
- *
- アブデラの守りに死んだ
- 勇しいアガトオンを
- ここに葬ると町をあげて
- 悼み嘆いた、
- 血を嗜むアレースもなほ
- これほどの若者を
- おぞましい戦のくるめきの間に
- まだかつて斃さなかった故
- (注:アレースはギリシア神話の戦いの神) (A62頁、B211頁)
- *
- たたかひに雄々しかりしティーモクリトス、
- これぞその奥津城、
- アレースは勇者を吝しまず、
- 怯者ををしむ。
- (A62~3頁、B210頁)
- *
- 水をもて来い、酒をもて来い、
- おい、小姓よ、
- それから、花の咲きそうた挿頭を
- わしらに
- もて来てくれ、ああ、持って来るのだ、
- これから一つ
- 恋神どんと、取っ組み合いを
- してやるほどに。
- (B217頁)
- *
- ではもうわしを 酔いくれたまま
- 家へかへさぬと お言やるか・・・・
- (A63頁 B224頁)
- *
- くれおぷうろすの いとしさよ
- くれおぷうろすに 迷うたさうな
- くれおぷうろすを 見れど見あかぬ
- (A58頁、B219頁)
- *
- やさしい子よ、乙女のやうな眼ざしをして、
- こがれる私の
- せつない頼みも肯いてくれぬとは。
- 私の心の手綱をとって
- 引き廻しながら、一向それに
- 気もつかないで。
- (B218頁)
- *
- 瞳のやさしさは、
- 若やぎの
- まだ乳ばなれぬ
- 仔鹿のやう----
- 森中で
- 角をおふ 母鹿に
- おいてゆかれて、
- 惑ひおそれる----
- (A59~60頁、B223頁)
- *
- さてそれから 深紅の球 を私にぶつけながら、
- 金髪の愛神はきれいに刺繡をした
- 鞋の乙女と遊べといって、私に呼びかけるのだ、
- ところが、その娘は、構へもよろしい
- レスボスの女だもので、私の頭髪を
- 白いといって、兎や角と苦情を言い立て、
- 他の男の方ばかりを、夢中で見ている。
- (B216頁)
次に、古代ギリシア七大抒情詩人のうち、女流詩人として名高いサッポー(サッフォー)について簡単に述べてみよう。サッポーは、紀元前7世紀末頃、エーゲ海のレスボス島に生まれた。アナクレオンよりもおよそ70年ほど前の生まれである。彼女は、恋愛詩を情熱的に詠み、特に、女性に対する愛を歌った詩が多いこと、また、レスボスに若い女性だけを集めて教育していたことから、同性愛者と見なされてきた(女性の同性愛者を意味する「レスビアン」という言葉は彼女の出身地に由来する)。しかし、それは事実ではなく、彼女は実際に結婚したことがあり、「クレイス」という名の愛娘を持っているのである。サッポーの詩風には、美しく華やかな修辞法に加えて、男性にも劣らぬ力強さがあり、「アフロディーテー祷歌」などを読むと、まるで「万葉集」の長歌に接しているような思いがする。残念なことに、彼女の作品のうち、現存しているものは非常に少なく、中には断片に過ぎないものもある。それというのも、中世の時代に、彼女の詩は恋愛詩であるがゆえに反キリスト教的と断定され、コンスタンティノープルのギリシア正教総主教の命令により、その詩作の大部分が焼却されてしまったからである。今、辛うじて残っているのは、諸所の古書を漁ってやっと見つけ出されたもの、或いは遺跡より掘り出された崩れかけのパピルスなど、僅かな数の作品に過ぎない。貴重な文化財が多数失われたことは返す返すも痛ましいことである。
それでは、呉茂一訳のサッポーの詩をいくつか取り上げてみよう。
- *
- 星はあきらかな 月のあたりに
- かがやいた 姿をひそめる、
- 十五夜の 銀の光が
- 陸にあまねく 照りわたるとき。
- (A34頁、B181~2)
- *
- すず川のほとり
- からなしの 枝を鳴らして
- 風そよぎ 渡りゆく、
- 葉末のさやに とよめけば
- (A34~5頁、B176頁)
- *
- さながらに紅の林檎の
- 色づいて みず枝に高く
- いと高い 梢に高く。
- 摘む人の はて見おとしか、
- いや見落せばこそ、
- かひなとどかぬ
- その紅りんご
- (祝婚歌) (A37~8頁、190~1頁)
- *
- 夕星は、
- かがやく朝が八方に
- 散らしたものを、
- みな もとへ
- 連れかへす
- 羊をかへし、
- 山羊をかへし、
- 幼な子をまた 母の手に
- 連れかへす。
- (A39頁、B189~190頁)
- *
- 月は入り
- すばるも落ちて
- 夜はいま
- 丑満の
- 時はすぎ
- うつろひ行くを
- 我のみは
- ひとりしねむる
- (A41頁、B202頁)
- *
- もし母さまえ
- ほんにもう わたしや
- 機をおる気も 出ませぬえ
- やさしい人が 忘られぬ
- おもいに胸も けおされて
- (A37頁)
- *
- クレイスに
- われに愛しき娘あり、
- 金色の花にしも たぐふべき
- 姿せる クレイス・・・・いとほしき、
- これに換えては リューディアをこぞり、
- めずらしき・・・・とも
- われ(望まじ)
- (A42頁、B198~9頁)
さて、サッポーやアナクレオンの活躍した時代から遥かに降って、紀元前70年頃にシリア・ガデラ出身の詩人メレアグロスが一つの詩集を編纂した。それは、古代ギリシアの黎明期からこの詩人の時代までおよそ600年にわたり、ギリシア各地で詠まれた秀歌を集めたもので、「花冠(ステパノス)」と題された詩集であった。「花冠」は、その後長期にわたり次々に新しい詩が追加され、何度も編集し直されて、「ギリシア詞華集」として伝えられていった。人類最古の詩集の一つである。しかも、その影響がさらに西のローマ世界にも及び、カトゥルスやホラティウスなどのローマ人までもが、ラテン詩の形ではあるが、ギリシア抒情詩の新たな継承者として登場する。そして、細々と続けられていたその伝統は、14世紀初期に始まったイタリア・ルネサンス(文芸復興期)において人文主義者たちにより再発見・復活されることになった。さらに時代が降って17世紀初頭、驚くべきことに、ハイデルベルクの領主プファルツ伯の書庫において「ギリシア詞華集」の古写本が発見されたのである。それまで伝えられていた写本は、誤写や脱落が多く、恣意的な改変すらあって、完全には信用できる訳ではなかったが、唯一の底本としては価値あるものであった。しかし、このとき発見されたハイデルベルク写本はサッポーも含め数千編に及ぶ詩の大集成であって、旧来の写本を包括し、しかも内容も良質のものであった。これは、「ギリシア詞華集」のより完全な原典を提供することになる極めて重要な発見であった。それにしても、何故このように貴重な古写本がドイツのハイデルベルクに持ち込まれていたのであろうか。それについては、いろいろな事情を想像することができる。例えば、1453年、ビザンティン帝国(ギリシア)は隣の強国オスマン・トルコの攻勢を受け、ついに滅亡の憂き目に会うのであるが、その直前、ギリシアの多くの学者たちが書物を携え西欧目指して逃亡していた、その中にギリシア詩の写本があって、それが巡り巡ってハイデルベルクの領主の手に渡った。
「ギリシア詞華集」には、抒情詩だけではなく変わった詩も載っていて、中には「なぞなぞ」を詩にしたものが多数あり、そのうちの数十編は数学の問題なのである。例えば、「林檎を6人に分配するとき、1人目は全体の1/3を、2人目は1/4を、3人目は1/5を、4人目は1/8を、5人目は10個を取ると最後の1人には1個しか残らなかったとすると、始めに林檎は何個あったか」というようなものである。ディオファントスが著書に書いていたような問題に似ており、いずれも1次方程式を解くことに帰する単純なものである。この詩集がこのような形で数学史にも登場するということは、ギリシア数学との関連も考えられて非常に面白い。
また、興味深いことには、かの大哲学者プラトーンも若き時代には文学青年であったらしく、詩作を良くしたという。その詩が「ギリシア詞華集」に掲載されているので、呉茂一訳にて味わってみよう。
- *
- 星を眺めるわたしの星彦
- えい 大空ともなって
- たくさんな眼で、
- お前をふりさけ見たいもの。
- (B74頁)
- *
- わたしは林檎、わたしを投げたは、
- 誰かお前にこがれるお人。
- 何と肯いては下さるまいか、
- クサンティッペさま、え、
- 私とてもまた、お前さまとて、
- つひは色香の褪せる身なのを。
- (B76頁)
それから、「ギリシア詞華集」には大変風変りでユーモラスな詩も見受けられるので、最後にそれを一つ。作者ダーモカレースが師匠アガティアースの飼い猫を相手に話しかけている愉快な詩で、読んでいると猫の表情まで目に浮かんで来るようだ。
- 人啖ひの山犬と同類だぞ、何て悪い猫だ、お前は。
- アクタイオーンの飼犬の一匹なんだらう、きっと。
- 自分の旦那アガティアースさまの鷓鴣を喰っちまって、
- 人もあらうに御主人様を、引裂いたほど悩ませるとは。
- そいからお前はしやこばかり狙ってるんで、今じゃ鼠どもは
- 踊ってるんだぞ、お前の御馳走を攫ってってさ。
- (注:アクタイオーンとは、神話中の人物で、自分の飼い犬たちに咬み殺された。)
- (A152~3頁、B119頁)
今まで引用してきた2冊の呉茂一訳詩集「ギリシア抒情詩選」及び「ギリシア・ローマ抒情詩選」は、常に私の書斎の机の脇に置いてあり、気が向いた時に手に取っては、たまたま開いたページから読んだり、幾人かの作品を次々に拾い読みしたりして、飽きずに楽しんでいる。これらを読むにつけ、感に堪えないのは、今から2000年以上前の詩人たちが抱いていた感情や思いが我々現代人のものと少しも変わらないということである。
それと同時に、古くはホメーロス(紀元前800年頃)にまで遡るギリシア詩の流れが、七大抒情詩人の時代を経て、ギリシア古典文化全盛期(これはアテネの最盛期と言ってもよい)を通り過ぎ、やがて「ギリシア詞華集」に結集して流れ下り、さらにルネサンスの時代に至って、再び勢いを盛り返し、近代にまで及ぶ、その大河のような雄大さを痛感せずにはいられない。
(令和3年1月28日脱稿)