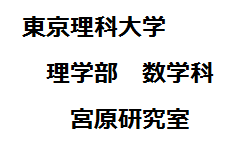続・大航海時代の幕開け
三年ほど前に、筆者は「大航海時代の幕開け」という記事を書き、浩洋会のホームページに掲載させて頂いた。それは、世界の歴史上最も重要な時代の一つであるいわゆる「大航海時代」の初期に、ヨーロッパ諸国を尻目にかけ、真っ先に大西洋に乗り出して、その時代を開いたポルトガル、スペイン両国の「功績」を述べたものであった。本記事はその続編であって、この両国のその後とその他の国々の「活躍」を紹介するものである。
ポルトガルは、アフリカ大陸の南端喜望峰を回りインドにまで達する航路を開拓し(1498年、ヴァスコ・ダ・ガマ)、その10数年後には、香辛料の原産地を求めて現在のインドネシアのモルッカ諸島にまで到達した。ポルトガルによって原産地よりヨーロッパに大量にもたらされる香辛料は、当時、胡椒貿易の中心であったヴェネツィアやその他の国々に甚大な被害を与えた。ヴェネツィアは香辛料をわずかしか入手できなくなり、市場の相場が急激に高騰した。ヴェネツィアはやむなくリスボンと胡椒の買い付けの交渉を行わなければならないほどであった。おごり高ぶるリスボンに対抗して、ヴェネツィアは懸命の反撃を試み、ヴェネツィア商人が直接インドにまで赴くようになった。粘り強い労苦の結果、彼らはアドリア海沿岸のスプリット(現在クロアチア領)に至るバルカン半島内の商業路を整備し、胡椒貿易のルートとして確保した。ラバと荷車による陸路輸送であった。やがて数多くのキャラバンがペルシャ湾から、あるいは紅海からスプリット目指してやって来るようになった。スプリットからヴェネツィアまでは距離的に近く、武装船団を組んでの海上輸送である。その年代を確定することはできないが、かくして、地中海の胡椒貿易は復活したのである。ポルトガルは人口が少なく国力が弱かったため次第に衰退し、1580年には隣国スペインに合併されることになる。
一方、スペインは、大西洋を真西に進めばアジアに辿り着けるだろうと予想するコロンブスを支援し(1492年)、ヨーロッパ人にとっては未知の大陸を発見した。スペインは新大陸においてポルトガルよりも大規模に植民地を形成し、活動領域を拡大していった。スペイン人は、16世紀半ばに、現在ボリビア領のポトシ銀山を手に入れ、その後メキシコにおいてもグアナフアトを始めとする数か所の銀山を獲得した。水銀アマルガム法という革新技術が発明されてから銀の増産が始まり、先住民であるインディオの奴隷労働によって生産された膨大な量の銀塊が本国スペインに送られるようになった。それまでヨーロッパの銀の供給源であったドイツの銀山は新世界の銀山に取って代られた。そしてドイツの多くの鉱山技師たちが新大陸へと派遣された。この銀の力によって、やがてスペイン王国は極盛時代を迎えることになる。
スペインに送られたこの大量の銀塊はどのように使われたのであろうか。16世紀、スペインはネーデルランド(現在のオランダ、ベルギー)を領有していた。世紀半ば以降、スペイン政府の強硬な弾圧に反発したネーデルランド人は、宗主国に反旗を翻し、大規模な独立運動を起こしていたが、この騒乱は泥沼戦争と化した。この戦費として、新大陸から運ばれて来る銀の大部分が消費されたのである。セビーリャに届いた銀塊は、直ちに、アントワープ(ベルギー)の取引所に送られた。アントワープは当時のヨーロッパにおける経済上の首都とも言うべき都市であり、ヨーロッパ各地より持ち込まれた多数の商品の集散地であった。前述の、インド航路を経てリスボンに輸送された香辛料も、アントワープに船で運ばれた後、各地の商人に売られていたのである。スペインの銀はアントワープにおいて銀貨に鋳造された。この銀貨が大砲や火薬の購入、傭兵の俸給などに当てられた。しかし、大量の銀貨が出回ったため、銀の相場が大きく下落し、スペイン王室は何度も破産宣告を行うようになった。とは言え、アメリカ大陸は尽きざる宝庫であった。その後も銀は続々とセビーリャに送られてきた。以前から、イギリスの海賊がスペインの船や領土を攻撃していたが、ついに、この海賊たちが、銀塊を積み込んでセビーリャからアントワープに向かう船を公然と襲い、銀塊を奪うという事件が発生した。イギリスは信用を失い、アントワープ市場での取引ができなくなった。そして、海路による銀の輸送は危険になり、この航路は一時閉鎖されることになる。
イギリスでは、15世紀半ば、英仏間の百年戦争がようやく終了したものの、すぐに、内戦(ばら戦争)が始まり、国内は覇権争いが収まらず、非常に混乱していた。そのため、イギリスは植民地獲得競争に大きく立ち遅れることになった。しかし、イギリス人が、ポルトガルのインド航路開発やスペインの大西洋横断を知っていながら、決して無為に過ごしていた訳ではない。イギリスの冒険商人たちが、アジアに到達する新しい航路を見つけるために、一つの企画を実行したのである。彼らは3艘の船団を組織して、ロンドンを出航し、何と、航路を真北に向けたのである。北極海を航行して、どこかでアジアに通ずる海路を発見できれば憧れの香料の島へ辿り着くことができるのではないかと考えたあげくの行動である。この3艘の船を率いて出航したのはリチャード・チャンセラーという男であった。1553年6月のことである。彼らは、ノールウェーの北端のノール岬を東に回ったところで、恐ろしい嵐に襲われ、チャンセラーの乗った船は他の2艘とはぐれてしまった。5年後にイギリスの捜索船が行方不明となったこの2艘を見つけ、曳航して本国に帰ったが、乗組員は全員船内で凍死していたという。一方、チャンセラーの船は、難を免れロシアの白海に入り込んで、ドヴィナ湾のアルハンゲリスク付近に投錨した。彼らはそこで船を捨て、陸路モスクワを目指した。距離にして1000キロに近い難義な徒歩行である。ついに彼らはモスクワに達し、暴虐な君主として有名な、かのロシア皇帝イワン(雷帝)に謁見したのである。雷帝は上機嫌で彼らに通商の特権を与えると約束し親書を持たせて帰した。すぐさま、ロンドンとモスクワの間に交易が始まった。ロシア産の蝋、鯨油、毛皮、木材、鱈などが、ロンドン商人のもたらすラシャや銀と引き換えに、ドヴィナ湾を経由して船でイギリスへ運ばれた。さらに、彼らが気づいたことは、ヴォルガ川を舟で下り、カスピ海に出て南下しペルシアまで行けば、香辛料や絹などが得られるということである。これは実現し、ペルシアからオリエントの素晴らしい品々がヴォルガ川を遡り、ドヴィナ湾でロンドン行きの船に積み込まれた。この交易は、9~10世紀にノルマンの盗賊商人たちが、商品を携えて小舟をかつぎながら、ロシアの川から川へと乗り継いで、ドニエプル川に出て黒海へと下り、都コンスタンティノープルに辿り着いたという史実を思い起こさせて大変興味深い。(拙文「東方のヴァイキング」を参照されたし。)
16世紀半ば、女王エリザベス1世の時代、度重なるイギリス海賊の銀船団攻撃に、業を煮やしていたスペイン王フェリペ2世は、ついにイギリスに対する開戦を決意する。そのきっかけは、前述のネーデルランド戦争においてイギリスがネーデルランドを支援すると公然と宣言したことである。両国の開戦は必至となった。エリザベスは、海賊の首領であった有名なフランシス・ドレイクをイギリス海軍の総司令官に任命した。このドレイクという男は一介の船乗りであったが、自分の船がスペインの海賊船に襲われ、すべての積み荷を強奪されたことから終生スペインに恨みを抱き、その後カリブ海の西インド諸島周辺に出没しては、主にスペインの貿易船に容赦のない襲撃を行い掠奪を恣いままにした。1577年には、世界一周の航海のため4隻の船団でプリマス港を出航した。大西洋を横断して南米大陸東沿岸を南下し荒れ狂うマジェラン海峡を通過したが、それに成功したのはドレイクの船だけであった。その後、彼は1隻だけで西沿岸を北上し、中南米のスペインの植民地や船を手当たり次第に襲撃して北米のオレゴン州辺りまで進んだ。そして、航路を西へ向けて太平洋を横断し、モルッカ諸島で香辛料を荷積みした後、インド洋を横断、喜望峰を回って帰国した。10か月ほどの航海であった。彼が獲得し持ち帰った略奪品や香辛料の半分はエリザベス女王に献上され、王室の財政を大いに潤した。その功績により彼は騎士(ナイト)に叙せられた。
さて、1587年、ドレイク率いるイギリス艦隊は、海戦の準備のためカディス港に集結していたスペイン艦隊に対し先制攻撃を仕掛けて大損害を与え、スペイン海軍は立ち直るために1年の月日を要した。ようやく態勢を整えたスペインは、120隻の軍船と乗組員を含めて約3万人の兵員を擁する大艦隊(無敵艦隊)をリスボンから出航させた。この艦隊はまずネーデルランドに行って、待機している別の艦隊と合流し、イギリスの領土に上陸する予定であった。無敵艦隊の出動を知ったイギリス艦隊は、英仏海峡で待ち構え、海峡の数か所で海戦が行われた(1588年、アルマダの海戦)。1か月足らずののち戦いは終わり、イギリスが完勝した。スペイン艦隊は半数以上の艦船と約2万人の兵員を失った。勝因は、イギリスの軍船が小回りがよく効き、スペインの大きな軍船を翻弄したこと、また、砲術に優れていたことである。それに加えて、スペイン側には、戦いの直前に歴戦の総司令官が急死し、後任に任命された総司令官は軍人ではなく行政官だったという不運もあった。無敵艦隊の敗北以後、ヨーロッパの制海権はスペインからイギリスに移り始める。
14世紀半ば頃から、オスマン・トルコ帝国は東ヨーロッパを侵略し始め、次の世紀にはビザンティン帝国(東ローマ帝国)の首都コンスタンティノープルを除いて、バルカン半島各地に触手を伸ばしていった。コンスタンティノープルだけは、周囲をトルコの領土に囲まれながら、その高く堅固な城壁と金角湾入り口に渡された軍船よけの鉄鎖によって、辛うじて護られていた。しかし、トルコは、途方もない額の金銭を投じて巨大な大砲をいくつも作らせ、また、鉄鎖を避けて牛に引かせた多数の軍船を山越えさせ金角湾の奥に浮かべるという奇襲作戦を実行し、さしものコンスタンティノープルもあえなく陥落した。1453年のことであった。長い命脈を保ったビザンティン帝国はついに滅亡した。1100年以上にわたりローマ帝国の首都であったコンスタンティノープルは以後イスタンブールと改称されることになる。オスマン帝国の勢力伸長は目覚ましく、遠くクリミヤ半島まで遠征し、黒海沿岸のほとんどすべてを支配下に置いた。さらに、シリア、エジプトからアルジェリアまでの北アフリカ一帯、そして、ギリシア、ブルガリア、セルビア、ルーマニアなどのバルカン半島全域、そればかりか、ハンガリーまでも領有したのである。16世紀半ば、大帝と呼ばれたスレイマン1世(在位1520~66)の時代にオスマン・トルコ帝国は最盛期を迎える。エーゲ海からヨーロッパ勢力を一掃し、海洋大国ヴェネツィアとも度々海戦を行った結果、トルコ海軍は一段と強力になった。トルコは、ヴェネツィアの造船所を模倣して、イスタンブールのガラタ地区に造船所を造ったが、それはヴェネツィアを遥かに凌ぐ大規模なものであった。
このように、ヨーロッパと対等に張り合えるほどの優秀な造船技術、操船技術、海軍力を持ちながら、しかも、ポルトガルのインド航路開発やスペインの新大陸発見を知りながら、不思議なことに、オスマン帝国は、大西洋やインド洋に乗り出すことはついに無かった。けれども、そのような意図が全く無かったとは言えない。と言うのは、例えば、以前にトルコは、紅海に乗り出すべくスエズ地峡に運河を掘り始めたことがあったし、また、インド洋を目指しペルシア湾の最奥部バスラ港を占領しようとしたこともあったからである。しかし、この国はこれらの計画をいずれも、途中で諦め断念していたのである。それ以後、トルコの軍船や商船の活動領域は地中海や黒海という内海のみに限られ、 これほどの強国が大海に雄飛することは絶えて無かった。オスマン人は海洋民族ではなかったということであろうが、実は、彼らの関心の中核はあくまでもヨーロッパ侵略にあって、その願望の念が極めて強かったからである。既にトルコはバルカン半島全域を支配していた。(これは現代に至るまで恐るべき禍根を残すことになった。)ハンガリーまで併合し勢力を拡張していたオスマンの次の目標は、彼らが「黄金の林檎の都」と称し喉から手が出るほど欲しがっていた「ウィーン」であった。当時のウィーンはハプスブルク家のオーストリア大公フェルディナントの統治下にあった。
ついに1529年、スレイマン大帝はウィーン攻略を命じ、大帝自身が軍を率いて出軍した。軍の総勢15万、そのうち3分の2は輜重隊で実戦部隊は5万であった。大砲などの武器や兵糧を運ぶのは輜重隊であるが、彼らはウィーンの手前まで荷を運ぶために、ふたこぶ駱駝の大群を使用した。当時のトルコでは駱駝は荷駄の一般的な運搬手段であって、イスタンブール港には絶えずおびただしい数の駱駝が大型船で運び込まれていたという。さて、スレイマン率いる大軍は、ウィーンへの遠征の途中で折悪しく降り続いた長雨のためにぬかるんだ道に大変に苦しんだ。兵や駱駝の疲労は甚だしく、時間を浪費し焦ったトルコ軍は、とうとう多くの大砲を途中で放棄し、進軍せざるを得なくなった。これは戦況に大きな影響を与えた。ウィーン市を囲む頑丈な城壁を破壊するには少数の大砲では難しく、攻めあぐねたトルコは坑道戦に作戦を変更したが、これもウィーンの密偵に見破られ防御された。何度も総攻撃をかけるも、ウィーン側の必死の抵抗に会い失敗が続く。そうこうするうちに早過ぎる冬が訪れ、雪が降り始めたのである。そこで、スレイマンは決断早く総撤退を命じた。しかし、退却軍をウィーン軍は追撃することができなかった。ウィーン側も、市の人口の3分の1ほどが戦死し、食料は残り少なくなり、また、傭兵に支払う金銀にも事欠くような状況だったからである。協力を依頼し期待していた近隣諸国の援軍も無く、フェルディナントはその薄情さを慨嘆した。ともかくも、ウィーンはやっとのことで厄介払いをすることができたが、執拗にヨーロッパに喰らい付いているトルコは、この3年後に再びウィーン攻撃を仕掛けて来た。これも失敗に終わったが、何と、この160年余り後に、トルコはウィーンをまたも包囲するのである。この国のヨーロッパ支配の執念深さには驚かざるを得ない。このように、ヨーロッパ侵略にいつまでも拘泥し無駄な精力の消費を続ける一方で、狭い地中海に閉じこもり、外洋に進出することを嫌ったオスマン・トルコは、古くなった行政制度と相俟って、緩やかに衰退の道を辿って行った。後年、トルコは多くの領土を失い、極盛時代の姿は見る影もなく、国力を増したヨーロッパ列強の為すがままにされることになる。
イギリス海軍が1588年にスペインの無敵艦隊を打ち破った後、ヨーロッパの制海権はスペインからイギリスへと移って行ったが、一挙にそうなったのではない。ネーデルランド戦争に勝利し、独立を勝ち取ったオランダや、ドイツとのイタリア戦争やユグノー戦争など国内の血生臭い覇権争いによる混乱から立ち直ったフランスが、ようやく植民地獲得競争に参入し始めたからである。オランダは、1602年に東インド会社を設立し、既にポルトガルがインドネシアのモルッカ諸島などに基地を造り、香辛料貿易に莫大な利益を上げていたところへ割り込んで来た。香辛料の島を巡り、両国の間に争いが始まる。そこへさらにイギリスも加わり、三つ巴の闘争となる。イギリスはオランダから香料島の一つルン島を奪った。他方、フランスは大西洋に乗り出し、西インド諸島のハイチを拠点として活動し、その上、アジアにも進出する。イギリスもジャマイカをスペインから奪い、さらに北米大陸東部沿岸地域を獲得して植民地とした。フランスは北米大陸の北部および内陸部を領有した。オランダもマンハッタン島を手に入れ、その地はニュー・アムステルダムと呼ばれていた。ルン島の所有を巡るイギリスとオランダの間の小競り合いが大きな戦闘に拡大し(英蘭戦争)、イギリスはニュー・アムステルダムを攻撃した。この戦いは2年も続いた後、両国の間に講和条約が交わされた。驚くべきことに、ちっぽけなルン島とニュー・アムステルダムが交換されることに決まったのである。オランダは北米大陸における拠点を失った。このニュー・アムステルダムが、今日、世界最大の都市ニューヨークとなった。多数の国が入り乱れて領土獲得を争ったこの時代の歴史は複雑極まりなく、さらに、裏の「大航海時代」とも言える各国の海賊の暗躍をも加えれば、その歴史を正確に記述することは大変に難しいだろう。大航海時代を通じて、結局、最後の勝利者はイギリスであった。19世紀から20世紀初期にかけて、地球上至る所に領土を有し、往年のスペインのように「日の沈まぬ国」と呼ばれ、世界に君臨する大海洋帝国となった。
参考文献
1 青木康征 ポトシ銀山 中公新書
2 加藤雅彦 図説 ハプスブルク帝国 河出書房新社
3 河北 稔編 イギリス史 山川出版社
4 川成 洋 図説 スペインの歴史 河出書房新社
5 菊池良生 ウィーン包囲 河出書房新社
6 薩摩真介 <海賊>の大英帝国 講談社選書メチエ
7 富樫瓔子 オスマン帝国の栄光 創元社
8 ブローデル,フェルナン(浜名優美訳) 地中海 I,II 藤原書店
9 ミルトン,ジャイルズ (松浦伶訳) スパイス戦争 朝日新聞社
10 横井裕介 図解 大航海時代大全 株式会社カンゼン
(令和3年8月7日脱稿)